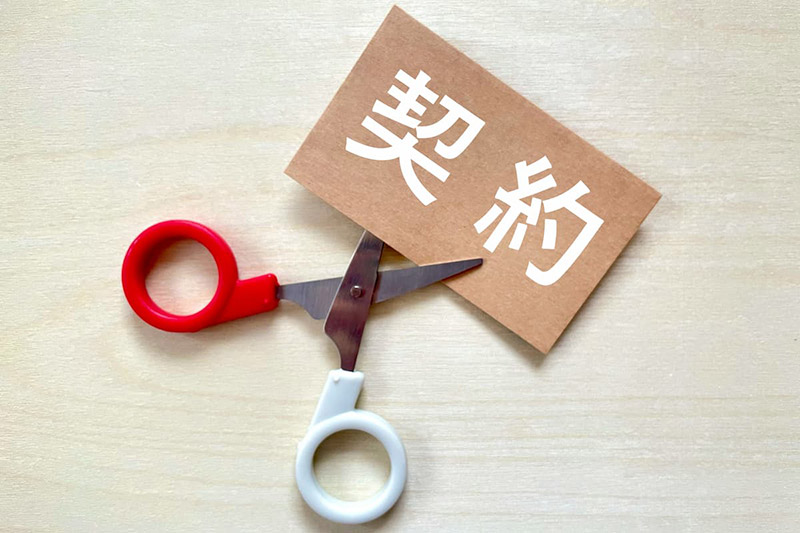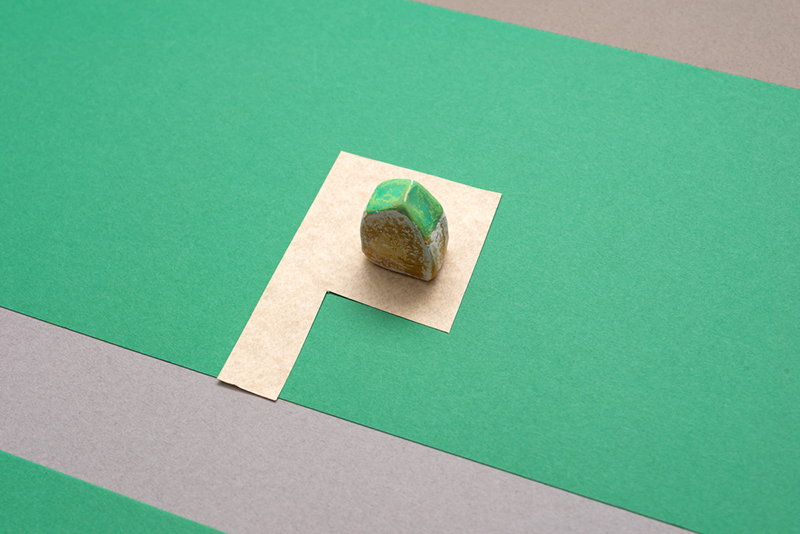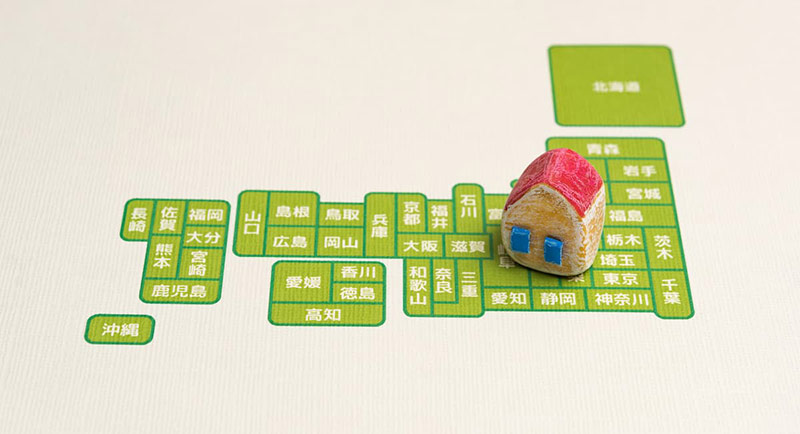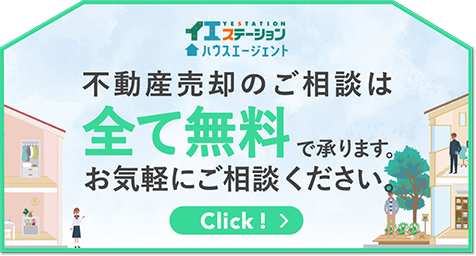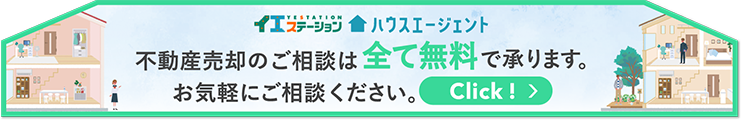物件状況報告書は売却時に作成義務がある?書き方や確認点も解説
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「物件状況報告書って何だろう?」
「作成は義務なのかな?」
「正しい書き方や、どこまで告知する義務があるのか知りたい...」
このような疑問をお持ちではありませんか?
物件状況報告書は、不動産取引において売主が買主に物件の状態を正確に伝えるための重要な書類です。
適切に作成することで売却後のトラブルを防ぎ、安心して取引を進められます。
今回のコラムでは、物件状況報告書の概要から作成義務の有無、書き方のポイント、確認点を解説します。

物件状況報告書は売却時に作成義務がある?
物件状況報告書とは、売主が買主に対して物件の現況を説明するための書類です。
中古物件の売買では特に重要視される書類で、建物の不具合や土地の状況、周辺環境について売主が知り得る範囲で記載します。
法的な作成義務はないが実質的には必須
結論から言いますと、物件状況報告書の作成は法律上の義務ではありません。
しかし、売主には「告知義務」があり、物件に関する重要な事項を買主に伝える必要があります。
例えば、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会では、売買契約時において、売主が物件について知り得ている事柄を「物件状況確認書(告知書)」に記入し、買主に説明することを推奨しています。
また国土交通省も、宅地や建物の過去の履歴や隠れた問題など、売主や所有者しか知り得ない情報について、告知書を通じて買主に伝えることで、将来の紛争防止に役立つという見解を示しています。
つまり、物件状況報告書の作成は法律上の義務ではありませんが、後々のトラブル防止のためには作成することが強く推奨されているのです。
作成しないと損害賠償や契約解除のリスクも
もし売主が物件の欠陥や不具合を知っていたにもかかわらず、買主に伝えなかった場合、売買契約書に「責任を負わない」と書いたとしても、売主は責任(契約不適合責任)を免れることができません。
具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
- 修理費用の負担:買主から「この不具合を直してください」と修理を求められる
- 契約解除:「こんな状態とは知らなかった」と契約自体を取り消される
- 損害賠償:「知らされていれば別の物件を選んだ」などとして損害賠償を請求される
上記のようなトラブルを避けるためにも、売主が知っている物件の状態は全て物件状況報告書に記載し、買主に伝えておくことが大切です。
買主が不具合を知った上で購入を決めた場合は、売主はその不具合について責任を負う必要はありません。
物件状況報告書を作成して物件の状態を正確に伝えることは、売主自身を守るためにも非常に重要だといえるでしょう。
物件状況報告書の書き方や作成時の確認点もチェック

物件状況報告書を作成する際は、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
基本的な書き方や作成時の確認点を解説します。
物件状況報告書の主な記載内容とは?
物件状況報告書の書式は不動産会社によって若干異なりますが、一般的には以下の内容を記載します。
<建物関係の項目>
- 雨漏りの有無と状況(発見していない・過去にあった・現在ある)
- シロアリ被害の状況(発見していない・被害があった・駆除歴)
- 建物の瑕疵(傾き・腐食・不具合等)
- 給排水設備の故障や漏水の有無
- 建物新築時の資料(確認済証・検査済証・設計図書等の有無)
- 住宅性能評価書や耐震診断の有無
- 増改築・修繕・リフォームの履歴
<土地関係の項目>
- 境界確定の状況や越境物の有無
- 土壌汚染の可能性
- 地盤の沈下や軟弱性
- 敷地内の残存物(旧建物基礎・浄化槽・井戸等)
<マンションの場合の追加項目>
- 共用部分の状況
- 管理組合の情報(管理費・修繕積立金の変更予定)
- 大規模修繕の予定
- 管理規約で定められた制限事項
<周辺環境に関する項目>
- 騒音・振動・臭気の有無(道路・電車・飛行機・工場・店舗等によるもの)
- 周辺環境に影響を及ぼす施設(ゴミ処理場、火葬場等)
- 近隣の建築計画
- 電波障害
- 近隣との申し合わせ事項(ゴミ集積場所、自治会費など特に引き継ぐべき事項)
- 浸水等の被害履歴(床上・床下を問わず、浸水の事実や周辺地域が浸水の多い地域であればその事実)
- 事件・事故・火災の履歴(自殺、殺傷事件等の心理的影響)
それぞれの項目について、「知らない」「発見していない」「あり」「過去にあった」などの選択肢から該当するものを選び、「あり」の場合は具体的な状況や対応履歴を記載します。
土地や建物の物理的な欠陥だけでなく、心理的な欠陥(事件・事故・自殺等)も記載対象となります。
心理的な欠陥のある物件については「事故物件は売却可能?定義から告知義務、高く売るコツまで徹底解説」で詳しく解説していますので、ご参照ください。
また、将来的に物件に影響を及ぼす可能性のある騒音・振動・臭気等の発生、近隣の建築計画などについても、知っている事実は全て記載しましょう。
物件状況報告書の記載は売主が行う
物件状況報告書は、必ず売主自身が記載する必要があります。
不動産会社が代行することはできません。
ただし、心理的な欠陥の告知範囲や近隣トラブルの記載の必要性など、「これは記載すべきかどうか」と迷う、売主だけでは判断が難しい場面もあるでしょう。
その場合は「書かなくていいだろう」と自己判断せず、不動産会社など第三者からの客観的なアドバイスを受けてくださいね。
契約前に状況が変わったら必ず更新を忘れずに
物件状況報告書は作成時点の状況を記載するものですが、売買契約締結までに状況が変わった場合は、必ず更新する必要があります。
例えば、物件状況報告書作成後に新たな不具合が見つかった場合や、近隣で建築計画が発表された場合などは、その情報を追記しましょう。
より正確に作成するためには建物状況調査が役立つ
物件状況報告書をより正確に作成するためには、建物状況調査(インスペクション)の活用が効果的です。
建物状況調査とは、国が定める資格を持った建築士が、建物の基本的な構造や雨漏り、外壁などの劣化状況を調べる検査のことです。
素人では気づきにくい不具合も客観的に把握できるため、より詳細で正確な物件状況報告書の作成に役立ちます。
建物状況調査を実施したかどうかも物件状況報告書に記載する項目となっており、調査報告書がある場合は、その作成年月日や調査実施者などについても記載します。
特に築年数が経過した物件を売却する場合は、建物状況調査の実施を検討する価値があるでしょう。
調査費用は発生しますが、「きちんと調査済みの物件」として買主からの信頼を得られ、購入の後押しになることも期待できます。
また、調査によって問題がないことが証明されれば、売却価格の維持にもつながります。
売却後のトラブルを未然に防ぐ投資と考えると、決して無駄ではありません。
雨漏りする家を売却する際の注意点については、「雨漏りする家を売却するには?高く売る方法も詳しくチェック」で解説していますので、あわせてご参照ください。
物件状況報告書は売却時の必須書類
物件状況報告書は法的義務ではありませんが、契約不適合責任を回避するために極めて重要な書類です。
物件状況報告書に記載された内容は、買主が「この状態で購入する」と同意した証拠となり、後々のトラブルを防止する効果があります。
適切に作成することで、売主・買主双方が安心して取引を進めることができるでしょう。
作成にあたっては、物件の状態を正直に記載し、不具合があれば具体的に説明することが大切です。
建物状況調査の活用も検討し、専門家の意見を取り入れると、より正確な報告書になります。
また、売主自身の責任で作成し、状況変化があれば速やかに更新することも忘れないようにしましょう。
不動産売却について悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。

いすみ店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
より安心していただけるよう、分かりやすい資料とわかりやすい説明を心がけております。
地元になくてはならない不動産屋としてクオリティの高いサービスをご提供してまいります。