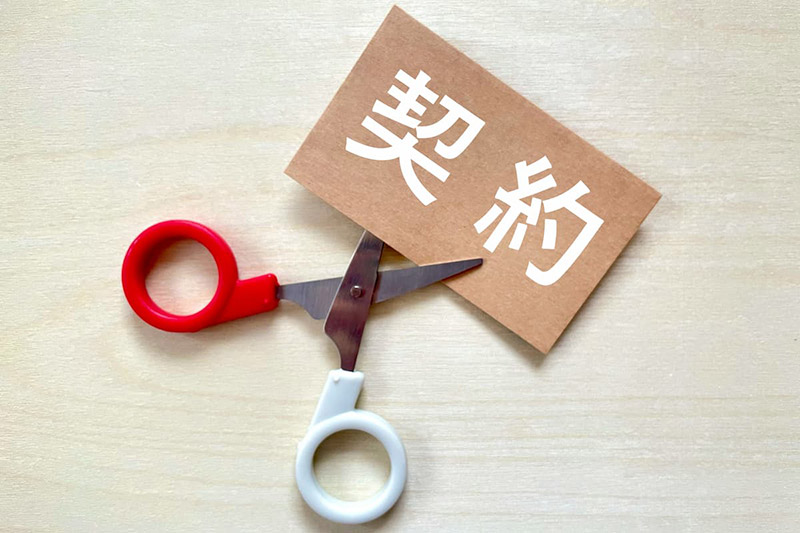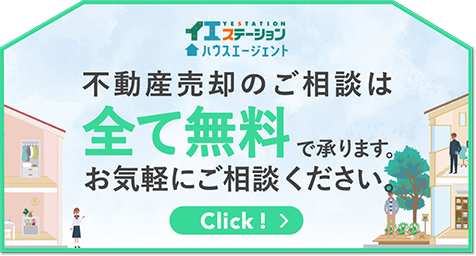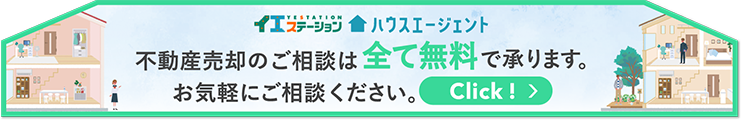農地は売却できる?宅地への転用条件や売却方法を解説
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「相続した農地を売却したいけれど、どのような方法があるのだろう」
「農地は規制があって売却が難しいと聞いたことがあるが、本当だろうか?」
このような疑問を抱く方は、少なくありません。
農地は農地法で厳しく保護されているため、一般的な土地に比べて売却しにくいですが、条件次第で売却できる可能性もあります。
今回のコラムでは、農地売却の規制の仕組み、宅地への転用条件と売却までの流れ・注意点を、わかりやすく整理しました。
農地の売却を希望される方は、ぜひ参考にしてください。

農地の売却は規制されているが可能?
日本では、田畑などの農地を自由に売買することはできませんが、次の2つの方法で手続きを踏めば売却が可能です。
- 農地としてそのまま売却する
- 宅地に転用した上で売却する
これは、食料生産を守る目的で制定された農地法が、農地の利用を強く制限しているためです。
農地の無秩序な転用や売買が進むと、農地が無計画に宅地や商業地へと変わり、将来的に食料不足や価格高騰を招くおそれがあるため、国は用途変更や権利移転に厳しいルールを設けています。
農地のまま売却する場合には制限がある
農地のまま売る場合、一定条件を満たす農業者または農地所有適格法人に限られます。
例えば、個人農家へ農地を売却する場合は、売却先が以下の条件を満たす必要があります。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
- 一定の面積(原則合計50a以上/北海道は2ha以上)を経営すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
参考:農林水産省「個人が農業に参入する場合の要件」
このような要件を満たす購入希望者は年々減少しており、農地のまま売却するのは非常に難しいのが実情です。
農地を転用すれば売却の可能性が広がる
一方、農地を宅地に転用して地目(登記簿上の土地の用途)を「宅地」に変更すれば、住宅・店舗・駐車場などさまざまな用途での活用が可能となり、市場価値が高まります。
売却先の対象も、農家に限らず、一般の個人や法人に広がります。
なお、詳しくは次のブロックで解説しますが、農地の全てが転用できるわけではなく、多くの場合は農地法に基づく許可申請が必要です。
宅地など一般的な土地に比べて売却が難しいことを、あらかじめ把握しておく必要があります。
農地を宅地に転用する条件や売却までの流れは?
農地を宅地に転用するために必要な条件・手続きを確認しましょう。
農地を宅地に転用するための2つの条件
農地を宅地に転用するには、「立地基準」と「一般基準」という2つの条件をクリアする必要があります。
①立地基準
立地基準とは、その農地が宅地転用に適した場所かどうかを判定するものです。
下記の区分に示した通り、生産性の低い第2種農地や、市街地に囲まれた第3種農地、市街化区域内の農地などは、転用が認められる可能性が高くなります。
【立地基準の農地区分】
- 農用地区域/甲種農地/第1種農地:生産力が高い地域で、原則として転用不許可
- 第2種農地:条件次第で許可される場合がある
- 第3種農地:原則として許可されやすい
- 市街化区域の農地:原則として農業委員会への届出のみで転用可能(許可不要)
一方、農用地区域や甲種農地などの優良農地は、原則として転用が認められません。
②一般基準
立地基準をクリアしても、転用後の使い方が不適切だったり、準備が整っていなかったりすると、一般基準の審査を通過できません。
一般基準では主に、下記のような内容を評価し、基準を満たさなければ不許可と判断されます。
- 転用計画が現実的であるか(資金や許認可・同意などの裏付けがあるか)
- 転用によって周囲の農地に迷惑がかからないか
- 一時転用の場合はもとの農地状態に戻せるか
参考:農林水産省「農地転用許可制度の概要 -農地法(昭和27年制定)-」
具体的な利用計画がない投機目的の転用や、周辺農地に悪影響を及ぼす計画は認められません。
宅地転用から売却までの流れ
農地を宅地に転用して売却するまでの基本的な流れは以下の通りです。
①所有する農地の区分や所在エリアを確認する
まず、転用できるかどうかを調べるために、市役所や農業委員会で、農地の区分(第2種・第3種など)と、所在エリア(市街化区域かどうかなど)を確認します。
また、所在エリアについては、農地転用の手続きとは別に、その農地が農業振興地域(農振地域)内に含まれているかどうかも確認されます。
該当する場合は、立地基準/一般基準の審査に進む前に「農振除外」の手続きが必要です。
②不動産会社へ売却相談
不動産会社に相談し、適切な価格と売却戦略を検討します。
③買主探しと売買契約の締結
転用許可を前提に、買主と売買契約を取り交わします。
④農業委員会へ転用許可申請
必要書類(許可申請書、登記事項証明書、位置図、公図、事業計画書、資金証明書など)を揃えて、農業委員会に申請します。
⑤許可後に本登記・代金精算・引き渡し
転用許可の通知を受けたら、所有権移転登記をして、売主から買主へと土地の名義変更を行います。
買主から売買代金を受け取って、売買取引完了です。
地目が「田」でも売却成功した事例
本当に農地変更して売却できるのかと、不安に感じる方もいらっしゃると思います。
イエステーションでも、「相続した戸建を売却しようとしたところ、登記上の地目が『田』であった。売却できるのでしょうか?」という相談を受けた事例があります。
こちらの事例では調査の結果、現況は宅地であり、地目変更の手続きを行うことで売却可能と判明。
農業委員会と市役所での確認を経て、適切な手続きとサポートにより、無事に売却が成立しました。
▶お客様の相談例 地目が「田」に家が建っています
このように、農地転用での売却については、売却を任せる不動産会社選びが大切です。
「農地転用の実績があるか」「地元情報に精通しているか」を目安にすると、スムーズな売却に役立つアドバイスを受けられるでしょう。
農地を宅地に転用して売却する際に気をつけること

農地を宅地に転用して売却する際には、以下の点にご注意ください。
手続きに時間がかかる
農地転用の手続きは、思っている以上に長期化する場合があります。
許可申請から承認までは通常1カ月半〜2カ月程度(届出の場合:1週間程度)、農業振興地域の除外が必要な場合は1年以上を見込む必要があります。
売却を検討するなら、早い段階からスケジュールを逆算し、準備を始めることが重要です。
転用後はすぐに売却手続きへ移る
転用許可を得た土地は、申請時に示した用途以外に使えず、許可後に造成してから売るなどの行為は基本的に認められていません。
転用の許可が下りたらすぐに売却に進めるように、事前に購入者を確保しておきましょう。
売買契約は「転用許可を停止条件とする契約」にする
農地転用での土地売却に際しては、転用許可が下りなかった場合に備えて、「停止条件付売買契約」を締結するのが一般的です。
これにより、許可が得られない場合は契約を白紙解除でき、違約金などのトラブルを回避できます。
専門知識が必要
農地転用の申請には、自治体ごとに異なる書類や受付スケジュールがあり、法的にも複雑です。
不動産会社・行政書士など、農地転用に詳しい専門家のサポートを受けると、手続きがスムーズで確実になります。
なお、農地の面積が広いと、広さ特有の売りにくさもあります。
広い土地の売却方法や不動産会社選びのポイントについては、「広い土地を売却する方法は?売却が難しい理由や不動産会社選びのコツも」で詳しく解説しています。
各種費用や税金が発生する
農地を転用して売却する際には、下記の費用や税金が発生することも知っておきましょう。
- 仲介手数料(不動産会社への仲介報酬)
- 行政書士への報酬(農地転用手続きを依頼した場合)
- 譲渡所得税(売却益に課される税金)
- 印紙税(売買契約書の発行に課される税金) など
詳しくは、「土地の売却でかかる税金を解説!支払いスケジュールと節税方法も」で解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
農地を宅地に転用して売却するならは早めの計画がおすすめ
農地の売却は、一般的な宅地取引とは異なり、食料供給を守る目的で定められた農地法の規制が関わるため、手続きが複雑です。
とはいえ、宅地への転用を行えば、購入を検討できる層が一気に広がり、売却のチャンスは高まります。
転用には、立地基準と一般基準という2つの審査をクリアし、許可申請を行う必要があります。
さらに、許可を受けたら迅速に売却に移れるよう、買主の目途を立てておくことや、不許可リスクを回避するために停止条件付契約を活用することも重要です。
農地売却に明るい不動産会社や行政書士などの専門家と連携し、費用・税金面も前もって確認しておくと良いでしょう。
不動産売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。

いすみ店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
より安心していただけるよう、分かりやすい資料とわかりやすい説明を心がけております。
地元になくてはならない不動産屋としてクオリティの高いサービスをご提供してまいります。